本屋さんに行ったら、電車男の二番煎じが平積みになっていた。そういや最近どこの書店でもネット原作本と堀江本でいっぱい。週刊誌コーナーにはヤングサンデーがあり、原秀則の「電車男」がしぶとく連載されています。2ちゃんねるのテクスチュアを無視した『僕が生まれ変わるラブコメ』になっており、原秀則は嫌いじゃないけれど、こいつはちょっと読むに耐えない。一言で言えば「生まれ変わる『電車』を、みんながパソコンづたいに見守って励ます」ってなノリになっていて、明らかに2ちゃんの空気と違うのだ。
そこまで感じてはたと気がついたのだけれども、これって世間の人がネットに抱く、典型的なポジティブな感情ではないのだろうか。インターネットとは、狭義的には共通プロトコルでコンピュータを数珠繋ぎにしたプラットフォームでしかなく、そのはたらきは同じメディアであるテレビや書籍と異なり、ビジネスモデルとかお作法というものがまだ確立していないので、一般の人が認知するには、もうちょっと明確なイメージがいるんだろう。で、原秀則が描く美しい物語になるんである。
もちろん2ちゃんねるに見られるように、局所的には場のプロトコルがすでに成立しているのだろうけれども、普通のメディアに慣れている人にとっては、あまりにもメタすぎるマイナーコードでしかないのだ。『キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!』とか、ヤンサンで描いたところでウケるかどうか微妙すぎる。そういう意味では、多くのブログ本とかこの手の漫画は、ネットの慣習と一般認識のあいだにかかるブリッジなのかもしれない。
・・・しかしまあ、『ネット・コミュニティのエールを受けて、恋愛に立ち向かっていく僕』などという描き方はすごいものがある。今後バーチャルコミュニケーションの道具が進歩するにつれて、恋愛が面倒くさいと思っている人間がどんどんネットに閉じこもる方向にいくんではないか、じっさいのところ。
抽出された物語だけ読むと、なんだかネットはコミュニケーション能力のインキュベータみたいだが、実際のところ僕が想像してしまうのは、「MATRIX」に描かれたエネルギーを吸い取られる繭のイメージだ。なんだか小説が書けそうですね。
■他サイト
電車男について
『電車男』についての記事について・・・ (斬ノ伍)
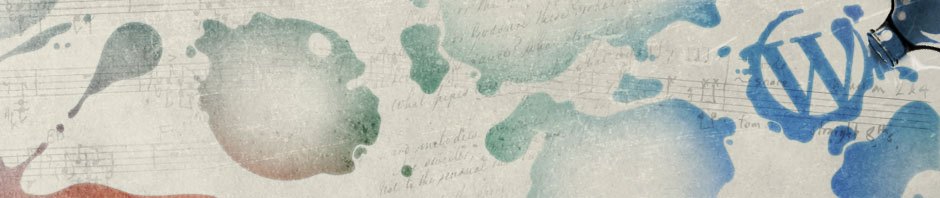
MATRIX的でありルサンチマン的でもありますが原秀則が描くということにやっぱり意義があると思うのです。パンピー化するということはパンピーに理解できる捉え方が一般化する必要があると思うのです。ちゃんと画面の向こうにもリアルがあるのだという認識が一般化すべきだと思うのです。
なるほど。。。
確かに、『バーチャルコミュニティ』なんて言い方自体がすでに実世界からの隔離であり、それを原秀則が一般化するというのは肯けます。
バーチャルとリアルは補完関係にあるのか、ある種のアンチテーゼに過ぎないのか。そのあたり、まだ僕の中では整理がついていないです。